デーモンコアと科学の原罪|全卓樹

ゲンロンα 2021年8月6日配信
それは鉛色の金属球であった。直径9cmほどの不気味な球体は、ベリリウムの半球殻の台座にぴったりと嵌っていた。そこから顔を出していた球体の上半面も、やはりベリリウムの半球殻の蓋でほぼ覆われている。横に立った若い男の片手が蓋にかかり、もう片方の手が持つドライバーがあいだに挟まって、二つのベリリウム半球殻が完全に閉じるのを防いでいた。
時は1946年5月21日、ロスアラモスの原子核研究施設の一室である。男の名前はルイス・スローティン、カナダのマニトバ大学で優等賞を総なめしてアメリカにやってきた、弱冠35歳の俊英物理学者である。部屋には他にも科学者6名と守衛1名がいて、スローティンの行う実験を見守っていた。鉛色の球体は臨界すれすれの量のプルトニウムである。これは東京に投下される予定だった第三の核弾頭そのものである。日本の降伏で用済みになって、製造元のロスアラモスに出戻ってきたのだ。
球の中では絶えず中性子が飛び交ってプルトニウムを分裂させ、そこからまた中性子が放出される。球のプルトニウムが仮にあとわずかに多ければ、プルトニウム分裂の連鎖反応が臨界に達して、この場に黙示録の世界が現前するであろう。
臨界は他の手段でも得られる。ベリリウムは中性子を反射するため、ベリリウムの蓋が近づくと、プルトニウム球から外に出て行く中性子が戻って、球内の核分裂が促進される。スローティンがドライバーを動かして、ベリリウムの蓋がより深く球体を覆うたび、シンチレーション・カウンターが激しくパチパチと光るのが見られた。
時は1946年5月21日、ロスアラモスの原子核研究施設の一室である。男の名前はルイス・スローティン、カナダのマニトバ大学で優等賞を総なめしてアメリカにやってきた、弱冠35歳の俊英物理学者である。部屋には他にも科学者6名と守衛1名がいて、スローティンの行う実験を見守っていた。鉛色の球体は臨界すれすれの量のプルトニウムである。これは東京に投下される予定だった第三の核弾頭そのものである。日本の降伏で用済みになって、製造元のロスアラモスに出戻ってきたのだ。
球の中では絶えず中性子が飛び交ってプルトニウムを分裂させ、そこからまた中性子が放出される。球のプルトニウムが仮にあとわずかに多ければ、プルトニウム分裂の連鎖反応が臨界に達して、この場に黙示録の世界が現前するであろう。
臨界は他の手段でも得られる。ベリリウムは中性子を反射するため、ベリリウムの蓋が近づくと、プルトニウム球から外に出て行く中性子が戻って、球内の核分裂が促進される。スローティンがドライバーを動かして、ベリリウムの蓋がより深く球体を覆うたび、シンチレーション・カウンターが激しくパチパチと光るのが見られた。

スローティンはこの臨界実験を、これまで何度も繰り返していた。その日は同僚たちを招いての、ディスプレイ実験の晴れ舞台だったのである。
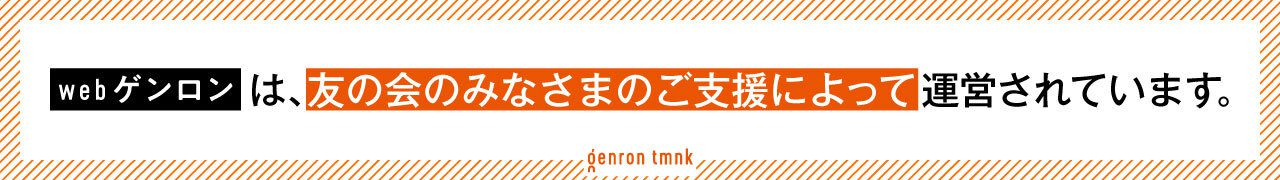

全卓樹
1958年京都府生まれ。高知工科大学理論物理学教授。東京大学理学部物理学科卒業、東京大学理系大学院物理学専攻博士課程修了。専攻は量子力学、数理物理学。ジョージア大学、メリランド大学、法政大学などを経て現職。著書に『エキゾティックな量子──不可思議だけど意外に近しい量子のお話』『銀河の片隅で科学夜話──物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異』など。




