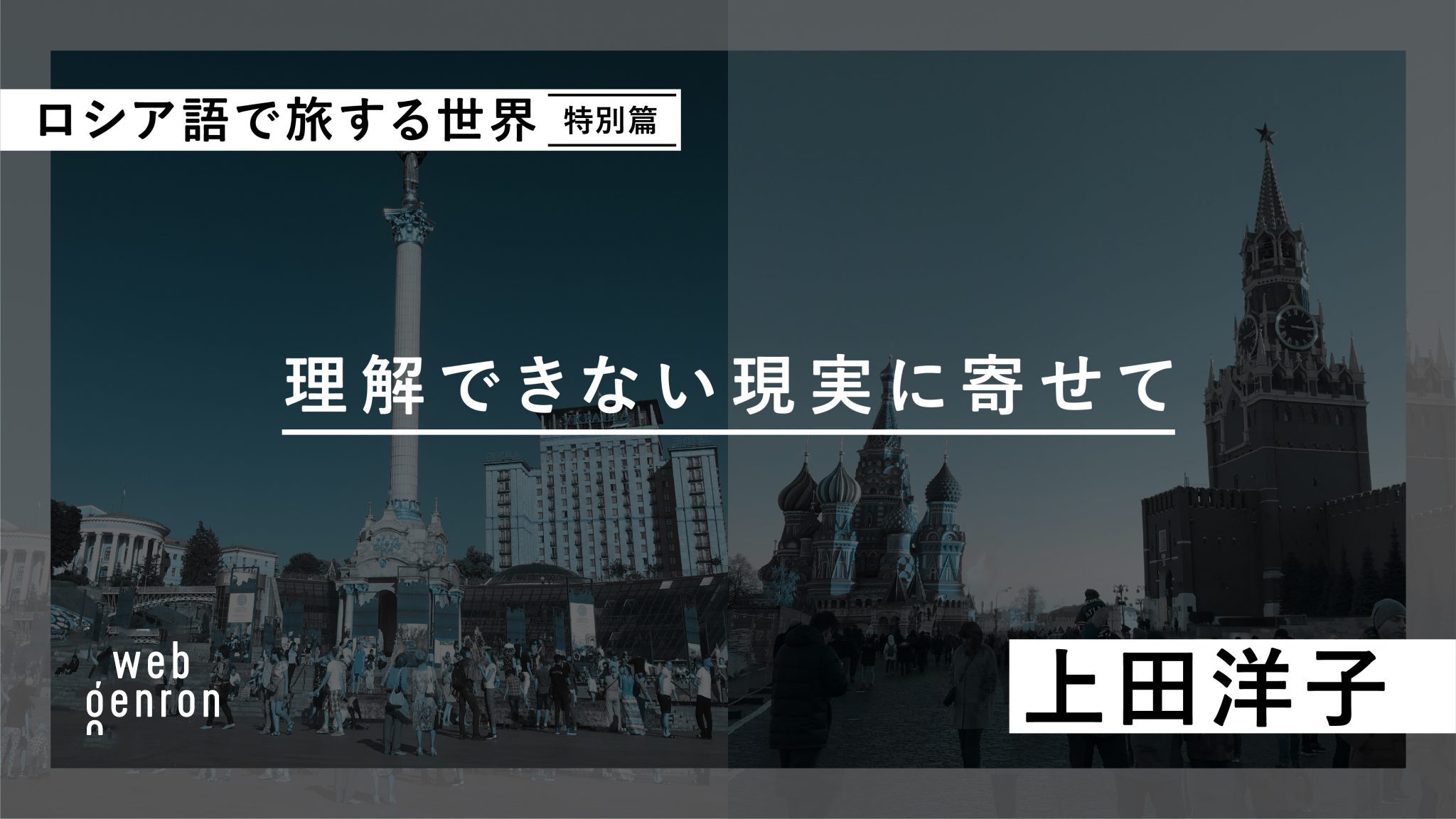ゲンロンβ71|編集長=東浩紀

収録記事を読む
2022年3月28日[月]発行
- 1|上田洋子 ロシア語で旅する世界 特別篇 理解できない現実に寄せて #37文学研究者として、ゲンロンの代表としてウクライナ・ロシア両国の人々と深く関わってきた上田洋子によるエッセイを公開します。友人の住む、縁の深い土地が戦地になるとは、どのような事態なのか。その心情を率直に綴ります。
- 2|乗松亨平 トラウマとイデオロギー――マルレーヌ・ラリュエル『ファシズムとロシア』評 #37プーチン政権がファシズム国家であるという目線に対し、冷静に分析を行なったマルレーヌ・ラリュエル『ファシズムとロシア』(東京堂出版)。ロシア文学・思想研究者の乗松さんが本書を通じ、いまロシアを動かすイデオロギーを考察します。
- 3|小松理虔 当事者から共事者へ 第17回 ウクライナ侵攻と共事の苦しみ #37ロシアによるウクライナ侵攻を前に感じた、当事者たりえない無力感。これまで「楽しい立場」として考えていた共事者の苦しみと、その立場が持つ強者性、そしてジャーナリズムのあり方を考えます。
- 4|君島彩子 自然発生的な祭壇と震災モニュメント――東日本大震災後の公共空間における「宗教的な形」の役割 #37東日本大震災の弔いのために沿岸部に仮設された祭壇は、どのように恒久的なモニュメントへと変化していくのか。その過程から読み取れる、「無宗教」を自認する日本人の宗教観を探ります。
- 5|山森みか イスラエルの日常、ときどき非日常 第4回 共通体験としての兵役(3) #37イスラエルの人々にとって重要な共通体験である兵役を紹介する、シリーズの第三回。今回は山森さんのご子息が入隊した後、どのような生活を送ったのかを描きます。実際の体験に根差したここだけのエッセイです!
- 6|本田晃子 革命と住宅 第9回 第5章 ブレジネフカ――ソ連団地の成熟と、社会主義住宅最後の実験(前篇) #37ブレジネフが書記長となり、ソ連各地には新たな団地「ブレジネフカ」が出現しました。その多様化ゆえの住宅格差を、当時の映画の場面から追求し、ソ連住宅の最後の実験の実像に迫ります。本田さんの人気連載、次号いよいよ最終回です。
表紙写真:2018年6月、チェルノブイリツアーでキエフを訪れた。現地コーディネーターのジャチェンコ氏(中央)とそのアシスタントのジェーニャさんとも長い付き合いである。5回目の開催を喜び、今後も続けていきたいと話していた。この回は毎日快晴で、青空と明るい風景が印象的だった。現在、ふたりとも戦火を避けてキエフを離れている。時間がかかるかもしれないが、いつか6回目を開催できたら嬉しい。(上田洋子)