批評再生塾定点観測記(3) 映画・課外活動|横山宏介

初出:2016年10月07日刊行『ゲンロンβ7』
第6回 「映画を『擬態』せよ」!
先輩は懐かしい。今回のゲスト講師である映画批評家の渡邉大輔は、批評再生塾第1期における、主催者の佐々木敦と東浩紀以外で講義を担当した最初の講師だった[★1]。思えばその際、(佐々木が選ぶ登壇者とは別に)渡邉が選んだ上位3名として挙げられたのが、批評再生塾で私の名が呼ばれた最初だった。その回では佐々木・渡邉の選出を合わせると、吉田雅史、上北千明、富久田朋子、野村崇明、横山宏介の名が挙げられており、得点レースの、そして最終課題の上位3名が出揃っていたことになる(後に総代となる吉田は佐々木と渡邉の両氏から選ばれ、かつその回の1位を取っている)。今振り返れば第1期の渡邉の回は、早くも天下分け目の戦いの様相を呈していた。
だから2期目の今回が「両雄相まみえる」という構図になったことも偶然ではないのかもしれない。この回までの累計得点31点で1位の山下研と、わずか3点差の28点でそれを追う福田正知が、共に登壇者として選出されたのだ。3位の谷美里が17点であることを考えれば、両名がツートップと言っていいだろう。共に批評家養成ギブスの修了生で、同人誌『ヱクリヲ』の編集メンバーでもあるふたりは、講評中もライバルとして扱われていた。残るひとりの登壇者もこの時点で4位(15点)の渡辺かをるであり、得点レースに大きな影響を与える回であったのは間違いない。
対決のテーマとなったのは映画。「映画を『擬態』せよ」[★2]と題されたその課題は、大澤聡、五所純子のものに続く、模倣を要求する3つ目の課題である。しかも今回、その対象となるのは映像作品の特徴そのものだ。映像の模倣を文字で行う必要がある以上、そこには必然的にアクロバットが求められる。講義中に渡邉が繰り返したように、批評対象となる作品選択の段階で勝負の大部分が決まる課題だったと言ってよい。

では登壇者たちはそれぞれ、どのような対象を選択し、どのような特徴に「擬態」したのか。
ライバルたる山下と福田の論稿は、ある点で似ており、ある点で対照的だった。
類似点は擬態のポイントである。山下は、講師の渡邉も本メルマガの連載「ポスト・シネマ・クリティーク」で前号に取り上げた映画『イレブン・ミニッツ』を、「対象作品における時間軸の遡行と混交を擬態」しつつ論じた[★3]。
一方の福田は、「五輪旗引継ぎ式の映像をイメージ群のコラージュ、パッチワーク的映像として捉え、最低限に意味は伝わるものの、所々に唐突な飛躍感のある文章を狙」ったという[★4]。つまり両者とも映像の「混交=コラージュ」性を模倣したというわけだ。
にもかかわらず、そのアプローチは正反対だった。その差異は、引用される固有名の数にあらわれる。山下は『イレブン・ミニッツ』を、無限に編集がきくデジタル編集映画の代表とし、対比としてフィルム映画『アラビアのロレンス』のモンタージュを取り上げ、両者を交互に論じるという手法を取った。その結果(おそらくは本人の意図に反し)、時間軸の乱雑な混交=デジタルシネマの特徴というよりも、フィルム映画的な、ふたつのシーンのモンタージュを模倣したような文章に仕上がっている。これも無意識だろうが、節を交互に区切る「■」と「□」の並びも、さながらフィルム側部のパーフォレーションのようである。とはいえ結論はモンタージュこそが映画であるというものであり、結果として論旨に馴染む擬態であった。
それに対して福田は、映像から喚起されたイメージを、ふんだんに盛り込んだ。「エドワード・ホッパーの《ナイトホークス》」にはじまり、「柄谷行人」、「あるぱちかぶと」と次々に繰り出される固有名は、数え方により多少増減するとはいえ両手ではとても数えきれない。むしろこちらのほうが『イレブン・ミニッツ』的な群像劇を擬態したかのようだ。好意的に読み込めば、それは映像で喧伝される「東京」の「交通都市」としての側面、あるいは「五輪」という世界的「祝祭」の猥雑さを捉えているとも言えるかもしれない。
こうして交互に眺めると、コラージュ性の擬態という点では福田の方が成功しているように見える。が、結果として直接対決を制したのは、山下の方だった。
勝因となったのは、文章の精緻さ。身も蓋もない言い方をしてしまえば、論旨の追いやすさである。比較対象を『イレブン・ミニッツ』と『アラビアのロレンス』に絞ったことにより、「デジタル/フィルム」「モジュール/モンタージュ」という対比が効き、分析が明快だった(とはいえデジタルな「モジュール」と「データベース」の差異が不問に付され、「この砂嵐が象徴するものは『モジュール』ではなく『データベース』である」という論旨の転換がうまくいっていないなどの瑕疵はある)。
ライバルたる山下と福田の論稿は、ある点で似ており、ある点で対照的だった。
類似点は擬態のポイントである。山下は、講師の渡邉も本メルマガの連載「ポスト・シネマ・クリティーク」で前号に取り上げた映画『イレブン・ミニッツ』を、「対象作品における時間軸の遡行と混交を擬態」しつつ論じた[★3]。
一方の福田は、「五輪旗引継ぎ式の映像をイメージ群のコラージュ、パッチワーク的映像として捉え、最低限に意味は伝わるものの、所々に唐突な飛躍感のある文章を狙」ったという[★4]。つまり両者とも映像の「混交=コラージュ」性を模倣したというわけだ。
にもかかわらず、そのアプローチは正反対だった。その差異は、引用される固有名の数にあらわれる。山下は『イレブン・ミニッツ』を、無限に編集がきくデジタル編集映画の代表とし、対比としてフィルム映画『アラビアのロレンス』のモンタージュを取り上げ、両者を交互に論じるという手法を取った。その結果(おそらくは本人の意図に反し)、時間軸の乱雑な混交=デジタルシネマの特徴というよりも、フィルム映画的な、ふたつのシーンのモンタージュを模倣したような文章に仕上がっている。これも無意識だろうが、節を交互に区切る「■」と「□」の並びも、さながらフィルム側部のパーフォレーションのようである。とはいえ結論はモンタージュこそが映画であるというものであり、結果として論旨に馴染む擬態であった。
それに対して福田は、映像から喚起されたイメージを、ふんだんに盛り込んだ。「エドワード・ホッパーの《ナイトホークス》」にはじまり、「柄谷行人」、「あるぱちかぶと」と次々に繰り出される固有名は、数え方により多少増減するとはいえ両手ではとても数えきれない。むしろこちらのほうが『イレブン・ミニッツ』的な群像劇を擬態したかのようだ。好意的に読み込めば、それは映像で喧伝される「東京」の「交通都市」としての側面、あるいは「五輪」という世界的「祝祭」の猥雑さを捉えているとも言えるかもしれない。
こうして交互に眺めると、コラージュ性の擬態という点では福田の方が成功しているように見える。が、結果として直接対決を制したのは、山下の方だった。
勝因となったのは、文章の精緻さ。身も蓋もない言い方をしてしまえば、論旨の追いやすさである。比較対象を『イレブン・ミニッツ』と『アラビアのロレンス』に絞ったことにより、「デジタル/フィルム」「モジュール/モンタージュ」という対比が効き、分析が明快だった(とはいえデジタルな「モジュール」と「データベース」の差異が不問に付され、「この砂嵐が象徴するものは『モジュール』ではなく『データベース』である」という論旨の転換がうまくいっていないなどの瑕疵はある)。
福田の論稿は自ら「唐突な飛躍感のある」点を真似たと述べる擬態が裏目に出て、論旨が散逸してしまった形だ。渡邉が「悪手」だと指摘したとおり、なまじ擬態が狙いどおりに機能したがために、論文としての基本的な展開が守られていなかった。この結果は皮肉にも思えるが、同じく模倣系の課題を出した大澤聡が、「あえて」をやるなら狙いが分かる文章にするスキルが要ると指導していたのを踏まえると、妥当な評価だろう。私見ではこの結果を招いたのは、対象作品の短さである。わずか2分の映像だけを対象に4000字の文章を書くのは厳しく、外部から他作品や思想の類を召喚することになるのは必定である。結果として、いやがおうにも文章はコラージュ的になるわけだ。その意味でも、勝負は作品選択の時点で決まっていたのかもしれない。最終的に、山下は16点、福田は8点と、ダブルスコアで勝敗が決した。
と、対比のために山下と福田に絞って書いてきたが、実は今回、渡辺の論稿[★5]はほかふたりとは違うベクトルで印象的だった(渡辺は前回登壇時にはプレゼンで異質な存在感を見せていたが、今回のプレゼンには特筆すべき点はなかった)。
彼が擬態したのは、映画『真夜中のピアニスト』における、「一人称映画を三人称的構成で作ったが故に、観客は主人公を『私』と重ねることもできず、かといって『彼』と突き放すことにもためらいが生まれるという構造」である。そのために「中間的立場」である「二人称」を用いて論文を書くという方法を採った。その効果として、小説のような魅力的な文体を生み出すことに成功している。二人称を用いた論稿としては、五所の課題への山下の応答があったが[★6]、「君」を作中人物に設定したことによって感情移入が促進されるという点で、今回の渡辺の方が(二人称の効果という点に限れば)うまくいっていた。
が、その結果として論旨自体が不明瞭になっていることは否めない。また「今回取り上げる『真夜中のピアニスト』」や「映画における一人称は、[中略]分けることができる」のように、明らかに「君」宛てではない説明的な表現も挟まれており、そもそも二人称は本当に一人称と三人称の中間なのかという問題も含めて、擬態にも突っ込みどころが残る。
文体や描写の魅力(今回の講義で渡邉が最も強調していたのは、批評における描写の重要性だった)を保ちつつ、論旨の展開力や論理性を高められれば、今後さらなる躍進が期待できる、そんなポテンシャルを感じさせる文章だった。彼には10点が与えられ、1位が山下、2位が渡辺、3位が福田という結果になった。

得点レース1位の山下(左)と2位の福田(右)。ツートップ状態の両者の明暗ははっきり分かれた
と、対比のために山下と福田に絞って書いてきたが、実は今回、渡辺の論稿[★5]はほかふたりとは違うベクトルで印象的だった(渡辺は前回登壇時にはプレゼンで異質な存在感を見せていたが、今回のプレゼンには特筆すべき点はなかった)。
彼が擬態したのは、映画『真夜中のピアニスト』における、「一人称映画を三人称的構成で作ったが故に、観客は主人公を『私』と重ねることもできず、かといって『彼』と突き放すことにもためらいが生まれるという構造」である。そのために「中間的立場」である「二人称」を用いて論文を書くという方法を採った。その効果として、小説のような魅力的な文体を生み出すことに成功している。二人称を用いた論稿としては、五所の課題への山下の応答があったが[★6]、「君」を作中人物に設定したことによって感情移入が促進されるという点で、今回の渡辺の方が(二人称の効果という点に限れば)うまくいっていた。
が、その結果として論旨自体が不明瞭になっていることは否めない。また「今回取り上げる『真夜中のピアニスト』」や「映画における一人称は、[中略]分けることができる」のように、明らかに「君」宛てではない説明的な表現も挟まれており、そもそも二人称は本当に一人称と三人称の中間なのかという問題も含めて、擬態にも突っ込みどころが残る。
文体や描写の魅力(今回の講義で渡邉が最も強調していたのは、批評における描写の重要性だった)を保ちつつ、論旨の展開力や論理性を高められれば、今後さらなる躍進が期待できる、そんなポテンシャルを感じさせる文章だった。彼には10点が与えられ、1位が山下、2位が渡辺、3位が福田という結果になった。

最後に短く全体の印象を書けば、映画や映像作品を見た際の抽象的な感覚への擬態を試み、結果として完成度自体を測りかねる出来のものが多かった。初回の講義で佐々木が述べたとおり、ある意味では作品体験を再現するのが批評である。が、そのためには抽象的な感覚や体験を、具体的な原因に還元する必要があるはずだ。渡邉が今回、描写の重要性を縷述していたこともここに関わるだろう。批評に求められるのは具体性であり、描写や構造の分析である。また福田のように、擬態に引っ張られ論旨が胡乱になる例も多く見られた。模倣を求められる課題も3度目なのだから、流石にもう少しバランスが取れてもよかったのではないかというのが率直な感想だ。
ここまで6回の講義が終わり、再生塾全体の行程の3分の1が済んだことになる。得点レースも中盤に入るわけだ。小沼純一による次回の課題[★7]は、そんなフェイズの移行を感じさせるものだ。これまでは批評の形式を意識させる縛りが多かったのに対し、次は端的に「なんでもあり」なのである。
──と、今回は批評再生塾の夏休みを挟んだ関係で、渡邉回のみの報告となる。とはいえ流石に文字数が淋しいので、休み中=課外での塾生たちの活動を少し紹介しておこう。
批評再生塾第2期では有志が集まって読書会を開催している。7月に行われた第1回では東浩紀の『存在論的、郵便的』が、8月に行われた第2回では柄谷行人『探究Ⅰ』がそれぞれ取り上げられた。いずれも批評の再生を志す上での必読書であり、早い段階で基礎を身に付けようという姿勢が見られる(ちなみにこの2冊は第1期の読書会──これを提言したのも今回講師の渡邉だ──でも取り上げた)。大澤聡による「『型』をインストールする」をテーマとした講義の効果だと言っていいだろう。次回は10月、課題図書はクロード・レヴィ=ストロース『月の裏側』が予定されている。前2冊に比べていささか(かなり?)マニアックなチョイスだが、こちらも中盤に入ったということだろうか。また、まだ企画段階ではあるものの、11月終旬を目処に1期生2期生合同の読書会が開催される(はずである)。こちらはおそらく私が取り仕切るので、(まだ腹案の域だが)ウォッチャーの方々にも参加してもらえればありがたいと思っている。
ここまで6回の講義が終わり、再生塾全体の行程の3分の1が済んだことになる。得点レースも中盤に入るわけだ。小沼純一による次回の課題[★7]は、そんなフェイズの移行を感じさせるものだ。これまでは批評の形式を意識させる縛りが多かったのに対し、次は端的に「なんでもあり」なのである。
──と、今回は批評再生塾の夏休みを挟んだ関係で、渡邉回のみの報告となる。とはいえ流石に文字数が淋しいので、休み中=課外での塾生たちの活動を少し紹介しておこう。
批評再生塾第2期では有志が集まって読書会を開催している。7月に行われた第1回では東浩紀の『存在論的、郵便的』が、8月に行われた第2回では柄谷行人『探究Ⅰ』がそれぞれ取り上げられた。いずれも批評の再生を志す上での必読書であり、早い段階で基礎を身に付けようという姿勢が見られる(ちなみにこの2冊は第1期の読書会──これを提言したのも今回講師の渡邉だ──でも取り上げた)。大澤聡による「『型』をインストールする」をテーマとした講義の効果だと言っていいだろう。次回は10月、課題図書はクロード・レヴィ=ストロース『月の裏側』が予定されている。前2冊に比べていささか(かなり?)マニアックなチョイスだが、こちらも中盤に入ったということだろうか。また、まだ企画段階ではあるものの、11月終旬を目処に1期生2期生合同の読書会が開催される(はずである)。こちらはおそらく私が取り仕切るので、(まだ腹案の域だが)ウォッチャーの方々にも参加してもらえればありがたいと思っている。
また、批評再生塾第1期生のその後の活動として、11月23日の文学フリマにおいて、1期生が編集する批評誌『クライテリア』が販売される。同イベントでは第2期生の山下、福田、横山祐が携わる総合批評誌『ヱクリヲ』も売られる予定であり、塾生が課題以外で書く文章が読める貴重な機会となる。批評再生塾に関心を持ったならば、ぜひ駆けつけて両誌を手に取ってみてほしい(というのも私は『クライテリア』『ヱクリヲ』両誌の編集に関わっているのだ)[★8]。
さて、そんな同人誌制作で培った基礎体力のせいか、やはり得点レースは依然『ヱクリヲ』勢が強い。山下が福田に大きく差をつけ48点でトップ。福田は37点で変わらず2位。3位は今回躍進した渡辺(26点)が谷(18点)を蹴落とし、順位に変動が起きた。1位と2位の差が大きく開いたが、提出者数の減少に伴い、一度に入手できる点数は跳ね上がっている。一発逆転とはいかないまでも、2回登壇すれば充分に3位圏内を狙える状況だ。繰り返せば、全行程の3分の1が終わった。そして未だ、3分の1しか終わっていない。観測の目は離せない。

さて、そんな同人誌制作で培った基礎体力のせいか、やはり得点レースは依然『ヱクリヲ』勢が強い。山下が福田に大きく差をつけ48点でトップ。福田は37点で変わらず2位。3位は今回躍進した渡辺(26点)が谷(18点)を蹴落とし、順位に変動が起きた。1位と2位の差が大きく開いたが、提出者数の減少に伴い、一度に入手できる点数は跳ね上がっている。一発逆転とはいかないまでも、2回登壇すれば充分に3位圏内を狙える状況だ。繰り返せば、全行程の3分の1が終わった。そして未だ、3分の1しか終わっていない。観測の目は離せない。

撮影=編集部
★1 第1期第3回「『ポスト映画の世紀』に、『映画(批評)』は再起動できるか」
★2 第2期第6回「映画を『擬態せよ』」
★3 山下研「モンタージュ・この映画的なるもの 『イレブン・ミニッツ』論」
★4 福田正知「灰のような、軽さ──リオ五輪閉会式について」
★5 渡辺かをる「『真夜中のピアニスト』 打ちのめされてもなお立ち上がる者に宛てた手紙」
★6 山下研「Re:Waltz with Bashir」
★7 第2期第7回「音楽、と、ことば」
★8 両誌の発刊情報についての詳細は、以下を参照されたい。 『ヱクリヲ』公式サイト http://ecrito.fever.jp/ Twitterアカウント @ecrit_o 『クライテリア』Twitterアカウント @CriCriteria
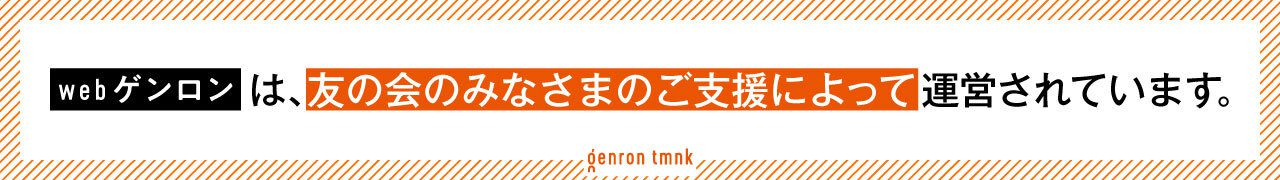

横山宏介
1991年生。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾第一期優秀賞。批評再生塾TAを経て、ゲンロン編集部所属。




