日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(9) たくさんのガリガリ君と、つくること──9月26日から10月22日|田中功起

ぼくはいま益子にいる。
慣れない iPad のキーボードで、こうして原稿の締め切りをすぎて慌てて書いている。いまいる実家の部屋は、ぼくが高校を卒業するまで使っていた場所。壁には高校のころに描いた風景画や自画像、ぼくが出ている新聞記事の切り抜きなどが無造作に貼られている。父が額装したり貼ったりしたものだ。しばらく前から物置状態になっていて、空き箱や壊れた健康器具たち、何に使うのかわからない複数の竹筒、放置された誰かの服などが乱雑に置かれている。
この家にはもうぼくの居場所はない。泊まる機会があれば、さながらキャンプをしている気分。自分の場所をなんとか確保し布団を敷く。窓や玄関は開放されているからさまざまな虫がやってくる。生まれながらに片足が不自由な犬(ラッキー)は屋外と屋内を自由に行き来している。ぼくはそのなかに異物として間借りをすることになる。
益子という地名を聞いて民藝運動を思い出す人もいるかもしれない。1920年代より批評家の柳宗悦と陶芸家の濱田庄司、河井寛次郎が中心となって進められた日本版のアーツ・アンド・クラフト運動だ。民藝運動が市井の人びとによる創造性に着目し、国内外のさまざまな無名の作り手たちの仕事をまとめたことは、インターネット時代の、現在のアノニマスな創造性にも関連づけられて語られている。かつて柳や濱田が見出したように、現在においても、つくることはもはやアーティストが独占的に行うことではないのだろう。YouTube を漁れば、誰もが何かをつくっている。
1924年、濱田は益子に移り住む。そして亡くなるまでここで制作を続けた。自邸の一部に、自ら国内外で収集した日用雑貨などを展示し、「益子参考館」という名前で一般にも開放している。いまで言う、デザイン・ミュージアムだ。自邸も含めた敷地内の建物は近隣地域から移築された古民家で、それらの建築も、だれかの制作のための「参考」にと集められたものだった。
民藝はそうして匿名のつくり手たちを称賛する。しかし同時に、いくつかの問題も抱えている。朝鮮半島でつくられた陶磁器に対する柳の視線に植民地主義的な側面があったことは免れない。だが、より本質的な問題はこちらだ。民藝という思想はアノニマスな活動を評価していた。にもかかわらず、職人の「作家性」を認めることによって、匿名だった職人たちは結果的に「作家」になってしまった。
益子でも、現在にいたるまで多くの作り手が作家主義に転じた。もちろんそれによって「益子焼」はブランド化できたとも言える。濱田以前に、民藝以前に「益子焼」があったわけではない。益子という地域で陶器が多くつくられていた、だけだった。濱田たちは、その素朴な陶器たちに美しさを見出した。いわば批評的な視点が介入することで「益子焼」は生まれたわけだけれども、同時にその批評的な視点によって、匿名性が担保していた陶器の素朴な美しさは失われてしまったのかもしれない。
益子にあった匿名的な創造性(の美しさ)は無自覚なものだったと思う。だから匿名的な創造性を評価する民藝という思想によって(「益子焼は○○なところがすばらしい」という視点によって)、逆説的に、無名の陶工たちは自身の作家性(他との違い)を自覚するようになる。益子の匿名性は、民藝という批評を介して、皮肉にも作家主義化したと言える。いや、それはちょっと言いすぎかな。
一方、今回の滞在で気づいたことがある。何気なく ZOZOTOWN の日用品ページを見ていると、益子焼の名が出てきた。ビームスが陶芸を扱っている。そこには「濱田窯」と書かれた、濱田庄司の窯を使ってつくられたコーヒーカップなどが複数出てきた。ぼくはなんだか少し感慨深かった。益子がビームスで扱われているということに対してではない。ぼくのなかでずっと疑問に思ってきた、先ほどの「匿名性の作家主義化」の問題がここで解決されていると感じたからだ。むしろ作家主義(濱田庄司というアーティストの名前)が匿名化(濱田窯という「窯」の名前への変化)していると思えたのだ。
もちろんその窯を引き継いでいるのは濱田の家族である。しかしそこには血縁を超えた複数性がある。現在の濱田窯の背景には、実は3.11の震災によって損壊した登り窯の復活プロジェクトがあった[★1]。登り窯というのは、階段状に房状の部屋が連なる、大量に陶磁器を焼くための巨大な窯で、いまでも薪を用いて焼成を行う。登り窯は煉瓦などによってつくられているため強い揺れがあれば容易に壊れてしまう。濱田邸にある登り窯も震災の影響で壊れてしまった。その修復に多くの人びとが関わっていた。
この「復活プロジェクト」によって濱田窯は家族の外へと開かれていく。修復された登り窯の窯焼きでは、さらに多くの陶芸家たちが関わった。薪割りから後片付けまで、全プロセスにそれらの陶芸家たちが参加することで、集団による協働制作と窯焼き技術の伝達が行われた。このような背景が加わることで、濱田窯は濱田庄司という作家名を歴史的な参照点とした個人(もしくはその家族の)「窯」から、複数の作家たちが集まるためのきっかけの場所に変化し、匿名的な創作の場所として再配置されたように感じた。窯に集う人びとの集団性。益子が、というか民藝が一周回ってもう一度原点回帰している。そう思う。
つくることはどのようにしてぼくのなかで始まったのだろうか。
最初につくることを意識したのは幼稚園のときだ。ダンスで使う亀の甲羅を描くために、四角い画用紙に緑色のクレヨンでずっと円を描いていた。終いには右手が緑だらけになり、それでも色をつけていた。ぼくの目的は甲羅を描くことでもあったけど、同時にその紙が甲羅そのものになることだった。クレヨンが一面に塗りたくられ紙そのものが光ってきた。そのときに先生に言われた、「こーちゃん、丸く塗っても丸くはならないよ」。ぼくにはいまだに彼女が言った意味がわからない。ぼくはぐるぐる円を描きながら緑色を塗りつづけ、クレヨンでテカテカになった紙を丸く切り抜き、紙の裏に紐をつけて少し反らせることで甲羅にした。それは紙であると同時に少し光沢のある亀の甲羅そのものに見えた。徒労感と充実感。つくることはそうやって始まったようだった。
ぼくはコロナ禍のなか、つくることから遠ざかっていた。
規模の大きな制作をする場合、自分が何を行いたいかを他者に伝える必要がある。アイデアを言葉にし、方向性や仕上がりのイメージを伝え、それに向けて協働する。計画があり、ミーティングがあり、複数の他者が関わるからそこには調整と交渉がある。ぼくにとっての制作とはそうした過程のすべてを含むものだ。コロナ禍で映像制作をすることがどのように可能なのか、ぼくには正直わからなかった。映像制作には撮影クルーを含めて多くの人が関わる。集団制作は、集まることは、感染リスクを意味する。だからぼくはつくることから遠ざかり、そうしているうちに自分が何をしているのかがわからなくなっていた。
人を集めることの意味をコロナ禍のなかで再びつかむまでに1年以上の時間が必要だった。9月に新作の撮影をしたんだけど、これについてはまたいつか書ければと思う。
最近になってやっと気づいたのは、つくることは何もそうした制作プロセスを経なくてもできるということ。いや、そんなことは当たり前だよね、ぼくはどうかしていたんだと思う。
そう、つくる行為は日常の所作のなかにもある。
ぼくの育児の経験は、どう、つくることに結びつくだろうか。
たとえば離乳食の盛り付けのアレンジメント、ベビーサークルのなかにあるものを使った即興的なインスタレーション、レゴブロックを別様に組み合わせたオブジェ。日々の生活は、同時に即興的な制作のオンパレードでもあった。娘はぼくのつくったものをすぐさま壊し、口に入れ、別のアレンジを、別のインスタレーションを、別のオブジェをつくり上げる。それらは見られることを意識しない、協働のパフォーマンスでもあったはず。つくることは壊すことであり、壊すことがつくることであるという目まぐるしい生成のプロセス。ぼくも彼女も、つくることの只中にある。
昨日の行為が今日の行為に繋がるときもあれば、まったくぜんぜん繋がらないときもある。それでも今日の行為はなにかしら明日の行為を準備する。ボタンを押すと童謡や言葉が流れるタブレット状の玩具を二つ並べて即興的に行われたDJイベント。でも彼女は翌日にはまったくDJ行為に興味を失くしてしまう。失われた興味は数日たって回帰することもある。
ひとりでつくることと、共につくることがいっぺんに起きていて、つくる行為の連続性のなかに育児があるように思えてくる。芸術の原初的な何かに触れているような感覚。他者との協働の始まりに位置するような関係性。そう考えれば、ぼくはコロナ禍のなかで決してつくってなかったのではない。むしろつくることそのものにある喜びに触れつづけてきたのかもしれない。もちろん育児はそんないい面ばかりじゃなくて疲労困憊することばっかだけど。
益子の実家は田中家が抱える問題をわかりやすく伝えてくれる。
父はよく「とりあえず」と言った。根本的に問題を解決するのではなく、場当たりで何かを行うことが、内装のそこかしこに現れている。壁も床も、その下にある何かを覆い隠すためにマットが敷かれたり、壁紙が貼られたり、板があてがわれたり、ときには白いガムテープが登場する。昔からある、いわゆるあの布ガムテープがぼくはとても嫌いだった。布ガムテープをしばらくたって剥がすと、その貼られていた面に粘着物質が張り付いてベトベトになってしまう。そもそも耐久性がない。父は、しかし、その白いガムテープを家のあらゆる場所に使っていた。床の段差に貼り、壁の隙間に貼り、天井の補強にも使っていた。すべては「とりあえず」で場当たり的だった。いまひとまずもてばいい。あとはなるようになる。場当たり性は柔軟な即興性を意味するから、良さでもあったのかもしれない。でも根本的な解決が必要な危機的な状況においてはまったく機能しない。深刻な病気は市販薬ではどうにもならないのと同じだ。
場当たり性は田中家の墓にもある。なぜかカロート(納骨室)がなく、敷地の空いているところに祖父も祖母も別々に埋まっている。曾祖父も曾祖母も独立した墓石が別々にあり、祖父祖母から少し離れたところにいる。ぼくはこの配置に禍々しいものを感じていて、母もずっとそう思っていたようだった。ばらばらに配置されている家族を一箇所に集めたいとぼくも思っている。父も、最近になってそんな話をしはじめていた。しかし彼は最後まで墓をリフォームしなかった。ぼくは田中家の墓をデザインし直すことで、悪しき「場当たり性」の連鎖を解消したいと思っている。
そうそう、今回は父の話なのだ。
父は田中家があまりにも貧乏であるから大学に行くことができず、高校卒業後すぐに働き、自分の望むような道に進むことができなかった。いまから想像すると、ぼくも実のところ父と同じように大学になんて行けるわけがなかった。ぼくが美大に入学した当時の田中家の経済状況からすれば、ぼくは美大を目指している場合ではなかった。まして私立の美大なんて無茶な話のはずだった。父は自分が断念したことをせめてぼくには実現させてやりたいと思い、大学に行かせてくれたんだと思う。
ぼくは自分がそうした貧しい家庭に生まれたということを、ずっと意識しないで生きてきた。なぜかはわからない。実家のある川向こうは貧しい家が散在する集落だったのだろうか。あまり覚えていない。貧しさを自覚したのは、大学に入ってからだった。当時非常勤講師だったアーティストの中村一美さんに、実家の内外を撮影した大量の写真群を見せると、「田中、大変だったんだな。俺も貧乏な家に生まれたからお前の気持ちがわかる」と言われた。彼はそれに加えて「お前はアーティストになるしかない」と言った。ぼくはどうやら貧しい家に生まれ、もはや逃げ道のない人生に足を踏み入れている、そういうことのようだった。
父は最後まで「大丈夫大丈夫」と言っていた。
でもぜんぜん大丈夫じゃなかった。末期癌の進行は思いのほか早く、緩和ケアのある病院に入院することになった。父は大腸癌の手術を数年前にしていたがどうやら転移していたようだった。
大腸癌だったことをぼくが知ったのは、父が手術をしてから1年以上が経過してからだった。父はぼくに心配をかけないようにとずっと知らせてくれなかった。癌は肝臓に転移していた。しかしどうやら手術ができないらしい。抗がん剤治療を今年になって行なっていたが、母はそれが転移に対しての治療だということをはっきりとは父から知らされていなかった。だから末期癌であることを転院先の病院で知らされた母はパニックになっていた。
ぼくは急遽、実家に帰った。
コロナ禍の入院では面会ができない。スマホ初体験の父にプリペイドのSIMカードを挿した古い iPhone を渡し、LINE通話の仕方を教えた。これで最低限、顔を見て話すこともできるし、孫の写真も受け取れる。父はふらついていたけどまだ自分で歩けたし、少しだけ食べることもできた。ぼくが実家に帰った日、父は麻婆豆腐が食べたいと言った。最初の入院の日、ぼくはこれが最後の瞬間になるかもしれないと思い、病室に向かうエレベーターに乗ろうとする父を引き留めハグをした。そんなことはしたことがなかった。
「大丈夫だから、功起」
ぼくは撮影のために京都にいったん帰り、ゲンロン総会に参加するために東京に行き、とんぼ返りで再び京都の自宅に戻った。妻のワンオペ育児状態を最小限にするためだ。
父は操作がわからないながらも LINE で母と話していたようだし、いままで嫌いだった鶏肉を病院で食べたらおいしく感じられたらしい。父は、元気だからとにかく家に帰りたいと医師に伝え、数日の点滴のあと一時外泊ということで家に戻った。治療のしようがないから、この外泊は退院ではないし、病気の改善を意味しない。点滴で栄養と水分を取ることができるから、2、3日は元気なんだと一ヶ月前は言っていた。このころにはほぼ毎日点滴をしないと体力を維持できない状態になっていた。それでも父は自宅で最後のときを過ごしたいと思っていたようだ。生魚が嫌いな父が、珍しく寿司を食べたいと母に伝えた。食感はわかるけど、味がほとんどわからないこのときの父は、いままで食べられなかったものをおいしいと言って食べていた。水分補給にもなるし暑かったのか、アイスもよく食べた。同じ種類のガリガリ君が冷蔵庫に大量にストックされていて、違う味はいらないのかなと思ったのを覚えている。
癌の進行は家族の気持ちなどお構いなしに早い。
気づいたときには足はむくみ、歩きづらくなり、黄疸ができはじめ、食べられるものが限られていく。場当たり的に祖父によってつくられた実家は段差が多く(場当たり性は祖父の代からつづいている)、父の部屋からトイレに行くのはなかなかしんどい。覚束ない足でトイレに行く途中で父は転倒し、足の皮がめくれてしまって再び入院することになった。
総会を終えて京都に帰った翌朝、母が泣きながら電話をかけてきた。
「お父さんが子どもたちに会いたいから家にまた帰ってくるって言っているんだよ」
再び一時外泊が認められて父は家に戻ることになった。父がはじめて本心を話していることに母は動揺していた。
荷物をまとめて、再度、益子に向かった。
そこからだいたい一週間、父は、自宅でほとんど寝たきりになりながら過ごした。録画していた時代劇「暴れん坊将軍」を見ながら、このとき唯一食べることのできたガリガリ君を食べていた。ぼくや妹、母がどこかの部屋にいて声が聞こえてくるだけで安心する、だから病院よりもここがいい、と父は話していた。そして、自分の車を廃車にするためには印鑑証明を取ってきたほうがいいとか、公共料金の支払い名義を母の名前にしたほうがいいとか、おむつではなくポータブルのトイレがいいとか、毎日なにかしらの買い物や手続きを家族で手分けして行なった。
母とぼくと、介護の仕事をしている妹の3人で交互に父のおむつを替えつづけた。子どものおむつ替えの技術が役に立ったが、大人の場合は足を上げるんじゃなくて身体を横に向けておむつ替えをするんだよと妹が教えてくれた。ガリガリ君しか食べていない父の緩くなった便からはワインの匂いがした。ヨーグルトも少し食べていたから体内で何かが発酵していたのだろうか。父と母の誕生日は同じなんだけど、ちょうど二人の誕生日が近づいてきた。地元の先輩がやっているお菓子屋さんでホール・ケーキを買ってきて祝った。二人の名前が書かれたケーキでこんなふうにお祝いしたことってあったかな、と母。父は少しだけケーキを口に入れた。このときに撮影した記念写真が最後に四人で撮影したものになった。
「四人で過ごしていると子どもたちが高校生だった頃を思い出すね」
母は父に言った。
父はガリガリ君を食べながらそれを聞いていた。
その後、父はよく眠るようになった。テレビからは時代劇の録画が流れていたけど、リモコンを持ったまま寝ていた。父は目が覚めるとガリガリ君を食べていた。祖父は最後、卵かけご飯しか口にできなかったらしい。ぼくは最後に何が食べたいと言うようになるだろう。
ラッキー(犬)はいままでも父の部屋で寝ていた。最後の数日間も、新調された介護用ベッドに寝ている父のそばで、彼は横になっていた。ゴールデンレトリバーの大きな身体を無理矢理ねじ込ませ、首だけを外に出した状態で、父の寝ているベッドの下に入り込むこともあった。以前にもましてラッキーは歩くのが億劫になり、散歩も嫌なようだった。
犬は人間の悪いものを吸い取ってくれる。ラッキーをよく連れて行く公園の犬仲間から母が聞いた話。本にも書いてあるって。
「悪いものを吸い取ってくれて、犬が人の代わりに死んでしまうこともあるよ」
「まさか」
父の悪いものはラッキーの手に負えないものだったようだ。
三日おきぐらいに病院に行くことになっていたが、父を車に乗せるのがぼくら家族だけでは難しくなってきた。1日でもいいからまずは病院にいようよ、次は介護タクシーか民間の救急車で家と病院を行き来することになるかも、でもひとまず病院の先生がどう言うかだよね。
「点滴したら家に帰りたい。家のほうがいい」
父はいつにも増して頑固だったけど、医師はこのままでは自宅で過ごすのも難しいと父と母に伝え、数日ひとまず入院することになった。翌日、忘れた iPhone の電源コードを届けた。看護師に言って、父と少しだけ話せるように繋いでもらった。父は、いまはしんどいから家に帰ってから話す、と言った。
外泊についての判断の日、介護タクシーか民間救急車を使うかどうか決めかねたまま病院に行く。母が医師と話すと、家に帰すことは難しいとなった。少しでも体力が回復したら自宅で過ごせるかもと思っていたけど、どうやら無理だった。
その夜、父から LINE の着信があり、今日はなぜ迎えに来なかったのか、と言われた。迎えには行ったけど、先生が無理だって言うから。家に帰りたい、家がいいよ、病院は嫌だ、ここはダメだ、家に帰りたい。
昼間は寝ているけれども、夜には少し元気になるんです、と看護師は教えてくれた。
看護師が撮影してくれた昼間の父の姿は、痩せ細って黄色くなり、テレビのリモコンを胸のあたりに持っていた。リモコンを持っていると安心するようだ。好きな時代劇を見ているつもりかもしれない。
「田中さん、何か言いたいことは?」
「ない」
と言って父は少し首を振った。
「じゃあ、かんばるよって言ってみる?」
「が、ん、ば、る、よ」
かすれた声だった。
父が亡くなったあと、病院から引き上げた荷物のなかに入院前に買った5本のガリガリ君があった。手付かずの4本と半分になった一本。最後に半分だけ食べられたようだ。
ぼくにできることはなんだろうと思い、父の遺影をつくることにした。まだ歩く元気があった一ヶ月前にぼくが撮影したポートレイト写真をベースに、iPad で修正を加えた。白い背景と白いシャツをタッチペンで描く。記念写真の父はいつも強ばった顔をしていたから、ぼくはその顔がほぐれるように声をかけて写真を撮っていた。「はーい、ニコニコして、ニコ、ニコ」。子どもに語りかけるようにぼくはそう言う。実家の前で傘をさして立っている父と母は少しだけ柔らかい表情をしている。
つくることはこんなふうにぼくの日常のなかに浸透している。
父にまだしゃべる元気があったとき、iPhone で彼の言葉を記録した。母と、将来この映像を見るぼくの子に向けて、父に語ってもらった。父は言葉に詰まると「とりあえず〇〇」と言った。場当たり性は彼の人生の最後までつきまとっていた。それもいまは懐かしい。
実家のそこかしこに貼られている「とりあえず」の白いガムテープ。もともとの素材が何だったのかわからなくなるくらいレイヤー状に重ねられた床。たくさんのつっぱり棒に吊り下げられたビニール袋。祖父によって建てられた場当たり的な建築のなかに充満した、場当たり的な配置や工夫による父のインスタレーション。父はずっと家を直し、屋根の色を変え、外壁を塗り、庇を拡張し、ものを再配置し、レイヤーを積み重ね、そう、何かをつくりつづけていた。制作の途中の継続。
つくることはそうして彼の日常のなかにも浸透していた。
彼は何も残さなかった。残せなかったのかもしれない。それでもぼくが引き継いだことがあるとすれば、「とりあえず」つくりつづけるという継続性、あるいは辛抱強さかもしれない。父は自分の行為が何を意味するのかを知らずにつくりつづけていた。父の行為はある種のインスタレーションをつくる長い長いプロセスだったと、ぼくは解釈する。
もちろんそんなことを話す前に父は去ってしまった。彼は死さえも「とりあえず」と思っていただろうか。真宗大谷派では、死はその瞬間に仏になることを意味するらしい。父の仏の姿があるとすれば両手にそれぞれガリガリ君とリモコンを持っているだろう、おそらく。
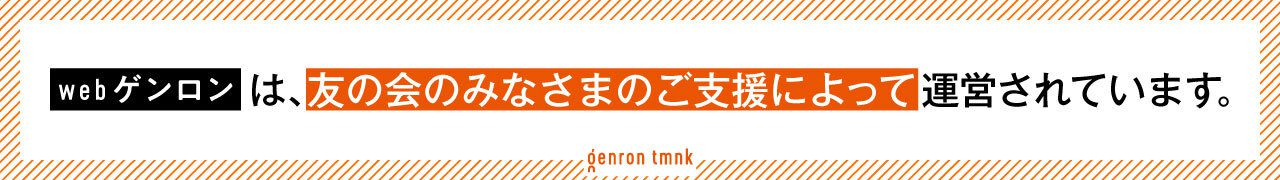

田中功起
1 コメント
- TM2024/02/06 17:05
益子が作家性を帯びて失い、再び場に戻って取り戻したもの。 それは日常の中で作るということだろうか。 匿名性の中で日常の器が作られ、BEAMSを介して誰かの日常に届く。 田中さんのお父さんが白いガムテープで続けたつくることは即興的に明日をつくることで、生きること自体がその積み重ねなのかもしれない。ガリガリ君を食べ続けることだってそうなんだろう。 そういうつくることにあるものは作家性が時に失わせるものなのかもしれない。 なにかつくりたくなりました。
日付のあるノート、もしくは日記のようなもの
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(14) 紛失したスーツケース、物質的変化、キッズスペース──7月16日から9月5日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(13) 手放すこと──5月10日から6月23日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(12) 生、あるいはウクライナ侵攻について──2月24日から4月13日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(11) パブリック・マネーの美学/感性論について──1月31日から2月17日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(10) 育児と芸術実践──11月29日から12月24日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(9) たくさんのガリガリ君と、つくること──9月26日から10月22日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(8) 未来の芸術と倫理の未来のため?──7月30日から8月27日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(7) 頭のなかの闇(その3)──5月15日から6月24日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(6) 頭のなかの闇(その2)──3月16日から4月19日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(5) 頭のなかの闇(その1)──1月21日から2月15日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(4) 怒りと相互確証破壊──11月19日から12月17日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(3) 高熱とケアのロジック──8月28日から10月2日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(2) ミルクとミルクの合間、そして芸術の経験──7月17日から8月15日|田中功起
- 日付のあるノート、もしくは日記のようなもの(1) 人生について考えると抽象が気になってくる──4月29日から6月10日|田中功起




