ゲンロンサマリーズ(1)『「当事者」の時代』要約&レビュー|徳久倫康

初出:2012年5月22日刊行『ゲンロンサマリーズ #3』
佐々木俊尚『「当事者」の時代』、光文社新書、2012年

要約
レビュー
ITジャーナリスト、佐々木俊尚の1年ぶりの単著。前作『キュレーションの時代』(ちくま新書)のテーマはソーシャルメディアであり、人びとの「つながり」によって情報が選別される時代が来た、と主張していた。事実佐々木はいまも毎朝、注目すべきニュースやエントリを紹介するキュレーションを実践している。
だが本書には、ITについての記述は少なく、代わりに語られるのは、毎日新聞記者時代の経験に裏打ちされた多くのエピソードである。なかでも「夜回り共同体」の紹介は、近年さかんな記者クラブ批判に対するカウンターとも取れ、じつに興味深い。
著者は震災を受け、マスメディアが被災者たちに期待した「物語」と、実際の被災者たちの意識のずれに、マイノリティ憑依の限界を見たという。だが、自分の理想を押し付けることなく、ありのままの他者と向き合うのは、とても難しいことだ。著者はその困難を強調した上で、それでも私たちが当事者となることの重要性を訴えかける。最後の数ページに記されているのは、ほとんど祈りのような文章だ。
ツイートだけではうかがいしれない著者の強い決意が本の随所から立ち上がる、メルクマールとも言うべき一冊である。
『ゲンロンサマリーズ』は2012年5月から2013年6月にかけて配信された、新刊人文書の要約&レビューマガジンです。ゲンロンショップにて、いくつかの号をまとめて収録したePub版も販売していますので、どうぞお買い求めください。
・『ゲンロンサマリーズ』ePub版2012年5月号
・『ゲンロンサマリーズ』Vol.1〜Vol.108全号セット
・『ゲンロンサマリーズ』ePub版2012年5月号
・『ゲンロンサマリーズ』Vol.1〜Vol.108全号セット
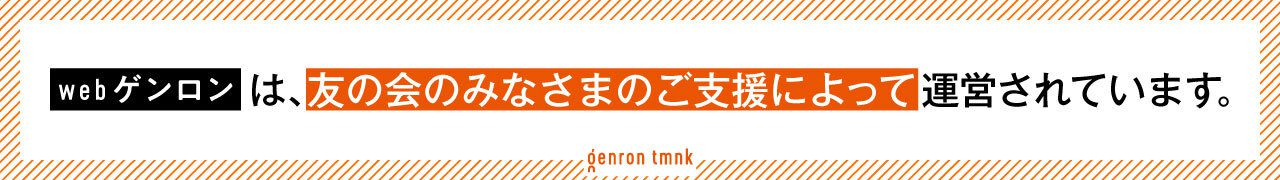

徳久倫康
1988年生まれ。早稲田大学文化構想学部卒。2021年度まで株式会社ゲンロンに在籍。『日本2.0 思想地図βvol.3』で、戦後日本の歴史をクイズ文化の変化から考察する論考「国民クイズ2.0」を発表し、反響を呼んだ。2018年、第3回『KnockOut ~競技クイズ日本一決定戦~』で優勝。
ゲンロンサマリーズ
- ゲンロンサマリーズ(13)『イメージの進行形』要約&レビュー|円堂都司昭
- ゲンロンサマリーズ(12)『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック』要約&レビュー|tokada
- ゲンロンサマリーズ(11)『地方の論理』要約&レビュー|徳久倫康
- ゲンロンサマリーズ(10)『独立国家のつくりかた』要約&レビュー|常森裕介
- ゲンロンサマリーズ(9)『ネットと愛国』要約&レビュー|峰尾俊彦
- ゲンロンサマリーズ(8)『ファスト&スロー』要約&レビュー|山本貴光
- ゲンロンサマリーズ(7)『統治・自律・民主主義』要約&レビュー|斎藤哲也
- ゲンロンサマリーズ(5)『(日本人)』要約&レビュー|徳久倫康
- ゲンロンサマリーズ(4)『一般意志2.0』要約&レビュー|入江哲朗
- ゲンロンサマリーズ(3)『団地の空間政治学』要約&レビュー|常森裕介
- ゲンロンサマリーズ(2)『謎の独立国家ソマリランド』要約&レビュー|海猫沢めろん
- ゲンロンサマリーズ(1)『「当事者」の時代』要約&レビュー|徳久倫康




