【 #ゲンロン友の声】ロブスターの権利?

先日、ニュースで「ロブスターは失神させてから調理を、スイスが保護規定定める」という記事を見ました。『ゲンロン0』で言及されているピーター・シンガー『実践の倫理』の一部の動物に人権を与えるべきという話と関係があるような、ないような気がしました。一般常識では(そして一部の条例などでも)、イヌ、ネコ、ハムスターなどの哺乳類を殺すことはいけいないとされていますが、虫や魚は平気で殺しています。その倫理的違いとはなんなのでしょうか?(東京都, 20代男性, 友の会会員)

ご質問、ありがとうございます。件の動きはむろんシンガーの哲学に関係しています。というより、日本ではあまり興味をもたれていませんが、動物の権利は欧米の応用倫理学ではけっこう話題にされていて、スイスの動きもその延長線上にあるものです。ヨーロッパは人権の概念を作った地域です。人権の歴史は人権の適用範囲の拡張の歴史でした。だとすれば、その概念がなぜ「人間」という生物学的な種を超えられないのかという議論が出てくるのは、ある種論理的な必然です。そういう意味でこれはあくまでも「論理的」な問題であり、「動物かわいそう」といった感情論に基づく議論ではないことを理解するのが大切です。「権利」とは、あるいは「主体」とか「快」とか「苦痛」とかいった概念はそもそも人類に限定されたものなのか、あるいはそれを超えられるものなのか?
これは今後、人工知能の発達に伴い、機械のほうからも問題になっていく問いであることでしょう。というわけで、ご質問への答えになります。ぼくたちは哺乳類を殺すのはなんとなく悪いような気がするが、虫や魚を殺すのは平気である、両者のあいだの「倫理的違い」はんなのかというご質問ですが、そんな違いはない、少なくとも論理的には簡単には打ち立てられない、だから困っているというのが倫理学の実情だと思います。それゆえ今回のような話もでてくる。最後にぼくの個人的な考えを言えば、おそらくは「主体」とか「快」とか「苦痛」とかいった概念なるものは、論理的に一貫した基礎付けを与えるのは無理だし、不可能なものなのではないかと思います。それらの概念は、具体的な現場から、ルソーの言葉でいえば「憐れみ」の発動の現場から、遡行的に見いだされるものでしかない。つまりは、「犬は苦痛の主体だから苦しめていけない」のではなく、「犬は苦しめてはいけない気がするので、ぼくたちはそこに遡行的に苦痛の主体を見いだす」というしかないものなのではないか。そこを無理して基礎づけようとすると、じゃあロブスターも主体だろうという話になってくる。まあ、そのような「無理な基礎付け」がぼくたちの共感の範囲を拡張してきた歴史もあるので、それはそれでいいのかもしれないし、件の規定を作った勢力もそこは確信犯的にやっているのかもしれません。あとは、未来の人類が、ロブスターを仲間だと見なすかどうかですね。(東浩紀)
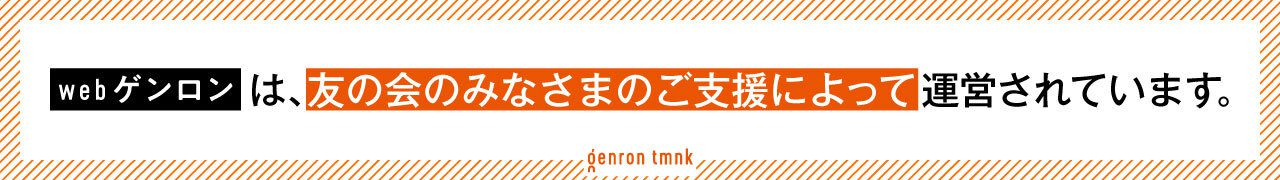

東浩紀
1971年東京生まれ。批評家・作家。東京大学大学院博士課程修了。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。著書に『存在論的、郵便的』(第21回サントリー学芸賞)、『動物化するポストモダン』、『クォンタム・ファミリーズ』(第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』、『弱いつながり』(紀伊國屋じんぶん大賞2015)、『観光客の哲学』(第71回毎日出版文化賞)、『ゲンロン戦記』、『訂正可能性の哲学』、『訂正する力』など。
ゲンロンに寄せられた質問に東浩紀とスタッフがお答えしています。
ご質問は専用フォームよりお寄せください。お待ちしております!




