【 #ゲンロン友の声】千葉雅也×東浩紀「モノに魂は宿るか――実在論の最前線」での東氏の発言について


まずは、質問者の方に失望を与えてしまったようで、ぼくの力不足をお詫びします。
そのうえで、質問――というか、ご質問は質問というよりも失望の表明でしたので、その失望を少しでも和らげるべく補足説明を記しますと、まずぼくは、魂は物理的には存在しないと考えています。つまり、何センチで何グラムといったかたちで物理的に計量できるものとしては、魂は存在しないと考えています。おそらくこの点については質問者の方も同意されるのではないかと思います(もし同意されないのだとしたら、残念ながらぼくとは物理的世界についての認識が異なるので、これ以上は対話はむずかしいかもしれません)。にもかかわらず、ぼくたちの多くは魂は「存在」すると感じる。だとするとつぎに問題になるのは、魂がもし「存在」するのだとしたら、それはどのような位相においてかということです。西洋の哲学は伝統的に、その位相を、「人間ではなく神だけがアクセスできる領域」だとか「いま存在するものだけでなく可能性まで含めた領域」だとか「経験できないのだけどその経験を支える条件の領域」だとかいった回答を与えてきました。この最後の回答がご指摘のカントのものなのですが、いずれにせよ、そういった回答もすべて、ではその領域が物理的に存在するのとは異なったしかたで「存在」するとはどういうことかといった肝心の質問にはたいして答えを与えていません(ちなみに、ご視聴いただいた番組で話題になったドイツの若い哲学者、マルクス・ガブリエルの主張は、要はそういうこと全部考えずに全部同じように存在でいいんじゃね?というもので、ラジカルといえばラジカルですが、思考停止といえば思考停止だというのがぼくの考えです)。
そこでぼくは、そのような「物理的存在ならぬ存在」はすべてぼくたちが物理的な世界を認識するときに起こるエラーとして捉えるべきだ、しかしそのエラーは不可避なので必ず「存在」するし、そのかぎりで魂は存在するとも言える、そのように主張しているのです。魂がエラーだというのは、魂が存在しないということではありません。それはエラーという審級で不可避的に存在するのです。この回答が、質問者の方の失望を少しでも和らげることができたとしたら、幸せに思います。(東浩紀)
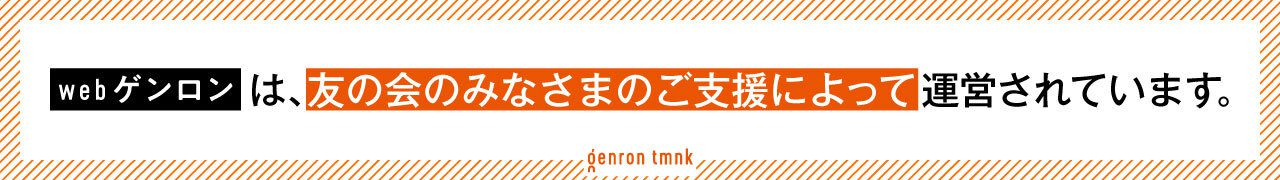

東浩紀
ゲンロンに寄せられた質問に東浩紀とスタッフがお答えしています。
ご質問は専用フォームよりお寄せください。お待ちしております!




