【 #ゲンロン友の声|023 】ヨーロッパに住む家族と分かりあいたいです

webゲンロン 2022年3月22日配信
私の姉は音楽家をしており、10年以上ヨーロッパに住んでいます。私の家族はもともと全員仲が良く、頻繁に姉と海外旅行などにも行っていました。コロナ禍になってからも、姉は年に1、2回来日してくれているのですが、最近どうも姉と馬が合いません。彼女はかなり我が道を行くタイプで、頻繁に日本人の考え方や、文化を否定してきます。そして、私が日本で働いていることを否定するようなニュアンスの事を言うことがあります。私は日本の音楽やアニメが好きなので、彼女が日本、そして私のことを否定する度に、とても悲しい気分になります。芸術家なので、とても感性が敏感なのだ、と思いながらも、度々ショックを受けてしまいます。私は姉と喧嘩をしたくなくて、いつも「そうかもしれないね」というフワッとした回答をするのですが、最近それが辛くてしょうがないです。家族のことが大好きなので、姉に対してこんな感情を持ってしまうこと自体が辛いです。このような場合、姉に対してどのような態度でいることが良いのか。家族の関係性について今まで体験したことがないくらい悩んでおり、可能であれば東さんのご意見を伺いたいです。何卒よろしくお願いします。(東京都・30代・女性・会員)

質問をいただいてから3ヶ月ほどが経過してしまいました。そのあいだに世界の情勢はまた大きく動きました。コロナ禍に続いてこんどは戦争です。ヨーロッパにいるお姉さまとの距離は、さらに開いているかもしれません。
ぼくには外国に住む家族はいません。親戚にも学者や芸術家はいません。それゆえ同じ状況に陥ったことはないのですが、ぼくは大学院ではフランス思想を研究し、知人には海外在住者もいるのでお悩みの事態を想像することはできます。ぼくも、ヨーロッパやアメリカを知的な背景にしているひととはあまり話が合いません。最近はそうでもなくなりましたが(たぶん彼らがぼくの存在を忘れてしまったためです)、むかしはよく批判もされました。それを悲しくも感じています。
ただ、それはしかたのないことだと思います。思想や価値観は環境の産物です。日本にいれば日本風に考えるし、ヨーロッパにいればヨーロッパ風に考える。住んでいなくても、日本のものばかり見ていれば日本風に考えるし、ヨーロッパのものばかり見ていればヨーロッパ風に考えることになる。それぞれの環境で「わたしは多数派とは違う、自分ひとりで考えている」と自負していたとしても、結局は個性の表現そのものに風土的な特徴が出ます。日本のアートはヨーロッパのアートとは違うし、日本の左翼もヨーロッパの左翼と違う。その違いは否定して解消されるものではないし、時間が経てば経つほど大きくなります。おそらく質問者の方が悲しく感じているのと同じように、お姉さまも悲しく感じているのではないでしょうか。
繰り返しますが、ぼくはそれはしかたのないことだと思います。そこでできるのは、せいぜいが悲しみを共有するぐらいのことでしかない。おたがい変わってしまった、でもしかたないねと。
逆にそこで一方だけが「正しさ」を主張し、他方の生き方を批判するようになってしまうと、関係は壊れてしまいます。ご質問を読むかぎり、お悩みの中心はまさにお姉さまがそのような「正しさ」の行動をとっていることにあるようです。けれど、そこで論争に巻き込まれてはいけません。むしろ、お姉さまのそのような態度を、彼女なりの悲しみの表現と受け止めてみてはいかがでしょう。質問者の方が「フワッとした回答」を返しているのと同じように、お姉さまはお姉さまなりに、むしろたがいの距離を縮めようとしているからこそ、質問者の方を批判する言い方をしているのだと。そして、むしろそれこそが、同じ問題に対する、日本風の対応とヨーロッパ風の対応の違いなのだと。
コロナ禍に戦争と、この数年で世界の情勢は様変わりし、かつてのように国境を超えて多くのひとが自由に行き来し、話をするのはむずかしい状況になってしまいました。コロナ対策にしても戦争への態度にしても、国家間だけではなく、それぞれの国内ですら大きな立場の差異があり、それに巻き込まれ家族内の人間関係もおかしくなっているひとは少なくないと思います。
けれども、そんなことで家族の仲が悪くなるのはバカげたことです。家族とはそもそも思想や価値観の一致を前提につくられた集団ではありません。それは偶然によってつくられたものです。だからこそ尊い。思想の不一致など関係なく、お姉さまとの偶然の関係を大切にしていただければと思います。(東浩紀)
ぼくには外国に住む家族はいません。親戚にも学者や芸術家はいません。それゆえ同じ状況に陥ったことはないのですが、ぼくは大学院ではフランス思想を研究し、知人には海外在住者もいるのでお悩みの事態を想像することはできます。ぼくも、ヨーロッパやアメリカを知的な背景にしているひととはあまり話が合いません。最近はそうでもなくなりましたが(たぶん彼らがぼくの存在を忘れてしまったためです)、むかしはよく批判もされました。それを悲しくも感じています。
ただ、それはしかたのないことだと思います。思想や価値観は環境の産物です。日本にいれば日本風に考えるし、ヨーロッパにいればヨーロッパ風に考える。住んでいなくても、日本のものばかり見ていれば日本風に考えるし、ヨーロッパのものばかり見ていればヨーロッパ風に考えることになる。それぞれの環境で「わたしは多数派とは違う、自分ひとりで考えている」と自負していたとしても、結局は個性の表現そのものに風土的な特徴が出ます。日本のアートはヨーロッパのアートとは違うし、日本の左翼もヨーロッパの左翼と違う。その違いは否定して解消されるものではないし、時間が経てば経つほど大きくなります。おそらく質問者の方が悲しく感じているのと同じように、お姉さまも悲しく感じているのではないでしょうか。
繰り返しますが、ぼくはそれはしかたのないことだと思います。そこでできるのは、せいぜいが悲しみを共有するぐらいのことでしかない。おたがい変わってしまった、でもしかたないねと。
逆にそこで一方だけが「正しさ」を主張し、他方の生き方を批判するようになってしまうと、関係は壊れてしまいます。ご質問を読むかぎり、お悩みの中心はまさにお姉さまがそのような「正しさ」の行動をとっていることにあるようです。けれど、そこで論争に巻き込まれてはいけません。むしろ、お姉さまのそのような態度を、彼女なりの悲しみの表現と受け止めてみてはいかがでしょう。質問者の方が「フワッとした回答」を返しているのと同じように、お姉さまはお姉さまなりに、むしろたがいの距離を縮めようとしているからこそ、質問者の方を批判する言い方をしているのだと。そして、むしろそれこそが、同じ問題に対する、日本風の対応とヨーロッパ風の対応の違いなのだと。
コロナ禍に戦争と、この数年で世界の情勢は様変わりし、かつてのように国境を超えて多くのひとが自由に行き来し、話をするのはむずかしい状況になってしまいました。コロナ対策にしても戦争への態度にしても、国家間だけではなく、それぞれの国内ですら大きな立場の差異があり、それに巻き込まれ家族内の人間関係もおかしくなっているひとは少なくないと思います。
けれども、そんなことで家族の仲が悪くなるのはバカげたことです。家族とはそもそも思想や価値観の一致を前提につくられた集団ではありません。それは偶然によってつくられたものです。だからこそ尊い。思想の不一致など関係なく、お姉さまとの偶然の関係を大切にしていただければと思います。(東浩紀)
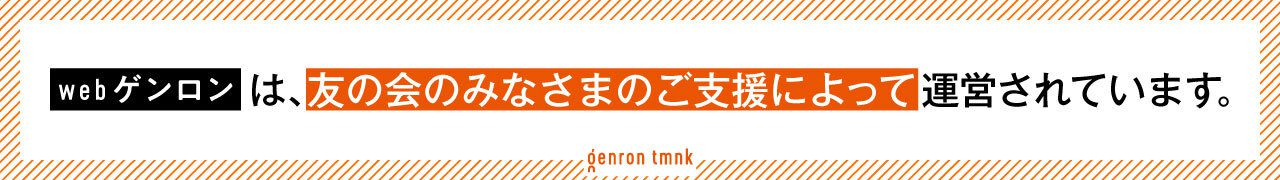

東浩紀
1971年東京生まれ。批評家・作家。東京大学大学院博士課程修了。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。著書に『存在論的、郵便的』(第21回サントリー学芸賞)、『動物化するポストモダン』、『クォンタム・ファミリーズ』(第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』、『弱いつながり』(紀伊國屋じんぶん大賞2015)、『観光客の哲学』(第71回毎日出版文化賞)、『ゲンロン戦記』、『訂正可能性の哲学』、『訂正する力』など。
1 コメント
- 匿名さん2022/03/23 18:27
哲学は必要ない。哲学から離れたいと思いつつも、また戻ってきてしまう理由がここにあります。哲学的な着想なしでは、人の意識を変えることはできないと、思うからです。
ゲンロンに寄せられた質問に東浩紀とスタッフがお答えしています。
ご質問は専用フォームよりお寄せください。お待ちしております!




