【 #ゲンロン友の声|024 】子どものまえで、過去の動画ばかり見てしまいます

webゲンロン 2022年8月22日配信
ゲンロンの皆様、こんにちは。
いつも楽しい記事や配信、企画等ありがとうございます。
今回は子育て中に感じた疑問をご相談したいです。
私事ですが、現在9ヶ月になる息子がいます。本当にかわいくて、毎日触れ合うのが楽しく、幸せな生活を送れています。
最近はスマホの画像もきれいで、また、アプリも充実しており、撮影した画像や動画をすぐに家族(祖父母など)で共有でき、日々の成長をすぐに他の家族に伝えることができます。と同時に、お気に入りの画像もすぐに再生できるので、本当に便利でありがたいなぁと感じております。
しかし、その再生した過去の動画を見て私がニヤニヤしているそばで、リアルな息子がリモコンをかじりながらこちらを見ていることがありました。そこで、「あれ?自分はこの過去の動画の息子がかわいいのか、いやいや現在目の前の息子がかわいいのか、どっちなんだろう」とか、「過去の画像ばかり見て、今目の前の成長を見逃しているのは、息子にとって良くないことなのではないだろうか」など、スマホに貯められたデータを見ながら不思議な感覚に襲われることがあります。
この今自分が陥っている、変な感覚、今をかわいがっているのか、過去をかわいがっているのかわからない感情の整理が言語化できず悩んでおります。
何となくゲンロンっぽい悩みな気がしたので投稿させて頂きました。
個人的な悩みですみません。
宜しくお願い致します。(静岡県・30代・男性・会員)
いつも楽しい記事や配信、企画等ありがとうございます。
今回は子育て中に感じた疑問をご相談したいです。
私事ですが、現在9ヶ月になる息子がいます。本当にかわいくて、毎日触れ合うのが楽しく、幸せな生活を送れています。
最近はスマホの画像もきれいで、また、アプリも充実しており、撮影した画像や動画をすぐに家族(祖父母など)で共有でき、日々の成長をすぐに他の家族に伝えることができます。と同時に、お気に入りの画像もすぐに再生できるので、本当に便利でありがたいなぁと感じております。
しかし、その再生した過去の動画を見て私がニヤニヤしているそばで、リアルな息子がリモコンをかじりながらこちらを見ていることがありました。そこで、「あれ?自分はこの過去の動画の息子がかわいいのか、いやいや現在目の前の息子がかわいいのか、どっちなんだろう」とか、「過去の画像ばかり見て、今目の前の成長を見逃しているのは、息子にとって良くないことなのではないだろうか」など、スマホに貯められたデータを見ながら不思議な感覚に襲われることがあります。
この今自分が陥っている、変な感覚、今をかわいがっているのか、過去をかわいがっているのかわからない感情の整理が言語化できず悩んでおります。
何となくゲンロンっぽい悩みな気がしたので投稿させて頂きました。
個人的な悩みですみません。
宜しくお願い致します。(静岡県・30代・男性・会員)

こんにちは。質問ありがとうございます。
書かれているお気持ち、よくわかります。弊娘はいまや17歳ですが、ぼくも彼女が小さなころはそのような「変な感覚」を感じたものです。子どもがあまりにもかわいいと、現実感がなくなりますよね。
さて、そのうえでの回答(?)ですが、ぼくが感じていた「変な感覚」は正確には少し違ったものでした。ぼくは、現実の娘と過去の記録された娘を重ねていたのではなく、現実の「いまここ」の娘を見ながら、むしろ、それが記録された過去になってしまった未来のことを思い浮かべていたように思います。ひらたくいえば、「いまここ」の娘を見ながら、つねに「ああ、この瞬間をのちかけがえのないものとして思い出すんだろうなあ」と、未来からの架空のノスタルジアを想像していたということです。気持ち悪いといえば気持ち悪い感覚ですが、子どもの幼い時間というのはあまりにも早く過ぎ去ってしまう。大人とのつきあいでは、今年のつぎは来年、そのつぎは再来年と同じ季節が繰り返されますが、3歳の夏と4歳の夏、5歳の夏はまったく異なるので、そのぶん時間を強く意識せざるをえない。それがぼくの場合は、つねに現在に未来を重ねるというかたちで出たんですね。その倒錯した感覚は、ぼくがむかし書いた小説『クォンタム・ファミリーズ』の基底にもなっています。
もう40年以上も前の本になりますが、かつて木村敏という精神科医が、人間の時間感覚には「アンテ・フェストゥム」(祭りのまえ)と「ポスト・フェストゥム」(祭りのあと)の二種類があり、そのどちらが優勢かで性格も決まるし、精神疾患もどちらを基礎にしているかで二分できるという議論を展開したことがあります(『自己、あいだ、時間』、1981年)。この分類を踏まえるならば、質問者の方は「幼い子どもがここにいる」という祭り(フェストゥム)を目の前にしながらもたえず祭りのまえに戻ろうとしていて、逆にぼくは祭りのあとのことばかり考えているといえるのかもしれません。しかし、いずれにせよ、その両者ともに祭りのなかにいることは変わりない。そして、上記のとおり娘もすっかり育ってしまったぼくとしては、いまだ祭りのなかにいる質問者の方が羨ましくてしかたありません。
幼い息子さんの子育て、いろいろとたいへんなこともあると思いますが、楽しんでがんばってください!(東浩紀)
書かれているお気持ち、よくわかります。弊娘はいまや17歳ですが、ぼくも彼女が小さなころはそのような「変な感覚」を感じたものです。子どもがあまりにもかわいいと、現実感がなくなりますよね。
さて、そのうえでの回答(?)ですが、ぼくが感じていた「変な感覚」は正確には少し違ったものでした。ぼくは、現実の娘と過去の記録された娘を重ねていたのではなく、現実の「いまここ」の娘を見ながら、むしろ、それが記録された過去になってしまった未来のことを思い浮かべていたように思います。ひらたくいえば、「いまここ」の娘を見ながら、つねに「ああ、この瞬間をのちかけがえのないものとして思い出すんだろうなあ」と、未来からの架空のノスタルジアを想像していたということです。気持ち悪いといえば気持ち悪い感覚ですが、子どもの幼い時間というのはあまりにも早く過ぎ去ってしまう。大人とのつきあいでは、今年のつぎは来年、そのつぎは再来年と同じ季節が繰り返されますが、3歳の夏と4歳の夏、5歳の夏はまったく異なるので、そのぶん時間を強く意識せざるをえない。それがぼくの場合は、つねに現在に未来を重ねるというかたちで出たんですね。その倒錯した感覚は、ぼくがむかし書いた小説『クォンタム・ファミリーズ』の基底にもなっています。
もう40年以上も前の本になりますが、かつて木村敏という精神科医が、人間の時間感覚には「アンテ・フェストゥム」(祭りのまえ)と「ポスト・フェストゥム」(祭りのあと)の二種類があり、そのどちらが優勢かで性格も決まるし、精神疾患もどちらを基礎にしているかで二分できるという議論を展開したことがあります(『自己、あいだ、時間』、1981年)。この分類を踏まえるならば、質問者の方は「幼い子どもがここにいる」という祭り(フェストゥム)を目の前にしながらもたえず祭りのまえに戻ろうとしていて、逆にぼくは祭りのあとのことばかり考えているといえるのかもしれません。しかし、いずれにせよ、その両者ともに祭りのなかにいることは変わりない。そして、上記のとおり娘もすっかり育ってしまったぼくとしては、いまだ祭りのなかにいる質問者の方が羨ましくてしかたありません。
幼い息子さんの子育て、いろいろとたいへんなこともあると思いますが、楽しんでがんばってください!(東浩紀)
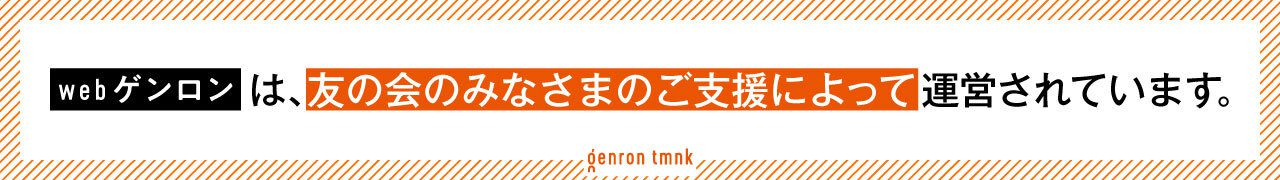

東浩紀
1971年東京生まれ。批評家・作家。東京大学大学院博士課程修了。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。著書に『存在論的、郵便的』(第21回サントリー学芸賞)、『動物化するポストモダン』、『クォンタム・ファミリーズ』(第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』、『弱いつながり』(紀伊國屋じんぶん大賞2015)、『観光客の哲学』(第71回毎日出版文化賞)、『ゲンロン戦記』、『訂正可能性の哲学』、『訂正する力』など。
ゲンロンに寄せられた質問に東浩紀とスタッフがお答えしています。
ご質問は専用フォームよりお寄せください。お待ちしております!




