観光客の哲学の余白に(21) 郵便的不安と生権力|東浩紀

初出:2020年07月17日刊行『ゲンロンβ51』
ぼくは1993年に、「ソルジェニーツィン試論」と題された2万字ほどの原稿でデビューしている。そのエッセイには「確率の手触り」という副題がついていた[★1]。確率はそれ以来、ぼくの哲学のキーワードとなっている。
ぼくの問題意識はこうだ。たとえば災害において、あるいは戦争や虐殺において、ひとは死ぬかもしれないし死なないかもしれない。そして、その選択はときにまったく無意味に、「確率的」にのみ決まる。ぼくたちは自分の死にいろいろと意味や必然性を見出しがちだが、ほんとうはその「かもしれない」の感覚のほうが重要なのではないか。ぼくはこの30年近く、そのことを訴え続けてきた。
ところでこの確率という概念には、哲学的にみるといささか厄介な性質がある。確率は英語では probability である。この名詞は probable という形容詞から派生している。そして probable は、判断を形容するものとしても対象を形容するものとしても使うことができる。
たとえば災害が起きたとして、遺体が出てきたわけではないが、状況証拠から考えて人物が巻き込まれて死んだことは十分にありうるとする。そのとき「問題の人物が亡くなったことは probable だ」と表現できる。しかしちがう使いかたもできる。これから災害が起きるとして、その人物を含め、関係者のあいだでは死者がおおぜい出るだろうと予測できたとする。そのようなときも「問題の人物が亡くなることは probable だ」と表現できるのだ。前者の事例ではだれが死んだかはすでに定まっている。不確定なのは認識だけだ。他方で後者の事例ではだれが死んだかは定まっていない。不確定なのは現実のほうだ。にもかかわらず、同じ probable ということばが使えるのである。ここでは英語の例しか出さないが、同じことはフランス語やドイツ語やロシア語の対応する単語についてもいえる。
したがって probability は、哲学的に厳密に考えると、すでに確定した事象についての認識が不確定であるさまを指すことも、いまだ事象そのものが確定しておらずどっちに転ぶかわからないさまを指すこともできる、あいまいな二面性をもった概念だということになる。サイコロ賭博は古代から知られていた。にもかかわらず、確率の数学的理論は、17世紀にパスカルとフェルマーが試みるまでだれによっても探求されなかった。科学史家のイアン・ハッキングは、まさにその遅れの理由を、 probability のこの二面性に求めている[★2]。
認識にかかわる probability について考えることは、不十分な証拠からどのようにして正しい判断を引き出すか、その推論法について考えることを意味している。だからその検討は、数学よりむしろ法学や弁論術と関係するものとなる。確率の数学的理論がつくられるためには、現実にかかわる probability が、認識にかかわる probability から切り離され、独立して知的に操作可能なものになる環境が必要だった。ハッキングは、フーコーの『言葉と物』を参照して、その環境がいわゆる「古典主義時代」のエピステーメーであることを示唆している。
認識にかかわる probability と現実にかかわる probability 。もう少しわかりやすく表現すれば、主観的な probability と客観的な probability 。日本ではこのふたつはおおまかに「蓋然性」と「確率」に訳しわけられている。だから両者の近さを意識しない。けれども日本人が混乱を免れているわけではない。そのことは、学問を離れて日常的な日本語を使うとき、「かもしれない」ということばに probable と同じ二面性が現れることを考えればわかる。主観的な蓋然性と客観的な確率の混同は、だれもがもつ脳の癖のようなものなのだろう。
ぼくは、蓋然性ではなく確率について考えている哲学者である。ひとは死ぬかもしれないし、死なないかもしれない。そのように記すとき、ぼくが考えたいのは、自分の死はすでに決まっているが、それがいつのことかわからないといった蓋然性(主観的な心理)が生み出す不安ではない。考えたいのはむしろ、ぼくが死ぬか死なないか、あなたが死ぬか死なないか、それはまだ決まっていないがいつかは確実に決まるはずで、そしてそのときの結果の偏りは数学で記述できてしまうという確率(客観的な現実)が生み出す不安なのだ。
デビュー作を書いたときには、ぼくはまだこのふたつの probability の差異を明確に理解していなかった。けれどもべつのかたちで触れている。
デビュー作の主題になっていたのは──いまから思えば、それは1990年代前半の日本で20代前半の若者が選ぶにしてはじつに唐突かつ時代錯誤な関心で、そのあたりにぼくの本質が現れている気がするのだが──、ナチスドイツのホロコーストにおけるユダヤ人の不安と、ソ連のスターリニズム下における囚人の不安のちがいである。ホロコーストもスターリニズムも何百万人もの犠牲者を出した。ユダヤ人もソ連の囚人も、ともに正当な理由なく自由を奪われ、辱められ、殺された。だから一般には両者は似た枠組みで理解されている。
けれどもぼくの考えでは、そこには見逃せない差異がある。ホロコーストにおいてはユダヤ人は殺されることが決まっていた。殺される理由も決まっていた(ユダヤ人だから殺される)。ただし彼らは、死がいつどのように、だれによってもたらされるかはわからなかった。彼らの不安はその運命の絶対性と、にもかかわらずの無知から生じている。つまり主観的な probability から生じている。
対してスターリニズム下の囚人は殺されることが決まっていない。彼らは殺されるかもしれないし、殺されないかもしれない。殺されるにしても、理由はわからない。ぼくがソルジェニーツィンの『収容所群島』を読んで知ったのは、そのような現実だった。だとすれば、ソ連の囚人たちが抱えた不安は、前述したユダヤ人の不安とは質的に大きくちがうというべきではないか。彼らの不安は、絶対的な運命への無知からではなく、むしろ運命の欠如=偶然性から、いいかえれば確率的な probability から生じているというべきではないか。
デビュー作のぼくはこの差異を、ホロコースト下のユダヤ人が抱いたのは「実存的」な不安だったが、スターリニズム下の囚人が抱いたのは「確率的」な不安だったといういいかたで表現していた。いまならばつぎのように整理することができる。ユダヤ人もソ連の囚人も、たしかに同じように、明日にでも殺される「かもしれない」との不安を抱いて生きていた。けれども、前者の不安が、死が蓋然的にしか認識できないことから生じていたのに対して、後者の不安は、そもそもの死が確率によってしか与えられない現実から生じていたのだと。
実存の不安と数の不安。蓋然性の不安と確率の不安。デビュー作を書いたあと、ぼくはデリダという哲学者を研究することになった。そこではデリダのことばを参照して、それぞれを「存在論的不安」と「郵便的不安」と名づけている。
認識の蓋然性が生み出す実存的で存在論的な不安ではなく、現実の確率的性格が生み出す数学的で郵便的な不安。繰り返すように、それこそがぼくが長いあいだ追い続けている主題である。
けれどもこれがなかなか理解されない。数の不安について話しても、読者はなぜか、むかしからよくある実存の不安についての話だと誤解してしまうのだ。ぼくが死ぬかあなたが死ぬか、その不確実性こそが重要なんですよと諭したとしても、そうですね、命はひとつですものね、いつ死ぬのかわからないのは怖いですよねと答えが返ってきてしまう。いやそうではないのだと反論しようとしても、存在論的不安と郵便的不安の差異を説明するのは意外とむずかしい。ふたつの probability を混同するように、ひとはふたつの不安を混同する癖をもっているようだ。
そんななか、最近考えているのは、確率あるいは郵便的不安の問題は、哲学の話であるのと同じくらい、あるいはそれ以上に政治の話だったのではないかということである。ぼくが死ぬかあなたが死ぬか、その不確実性こそが人間の不安を生み出すという認識にいたるためには、まずは、人間から死の固有性を剥奪し──ハイデガーによればその固有性こそが実存の条件だったのだが──、ぼくの死もあなたの死もすべてを「死者1名」に還元し処理してしまう、そういう残酷な「場」の存在を実感する必要があるのではないか。その「場」の存在が実感できないことには、郵便的不安の問題提起はおそろしく抽象的に響くにちがいない。
そしてその「場」というのは、けっして哲学的な想定ではなく、むしろ政治的な実体である。カンのいい読者であればお気づきのように、ぼくはここで、フーコーのいう「生権力」の話をしている。生権力とは、ひとことでいえば、人間を数として、家畜のように扱う権力のことである。生権力は19世紀に一気に開花し、それまでの「主権権力」すなわち王の命令にもとづく権力にとってかわり、統治の中心的な道具となった。そしてこの新たな権力の伸長は、さきほどのハッキングがべつの研究で示しているとおり[★3]、統計学の発展と不可分な関係にある。ヨーロッパは17世紀にふたつの probability を分割し、客観的な probability (確率)についての数学的理論を組み立て始めた。19世紀に入ると、その理論がこんどは主観的な probability (蓋然性)のほうに逆流し始める。ひらたくいえば、大量のサンプル──いまでいうビッグデータ──をもとに、直接には測定できない対象やいまだ確定していない事象について、確実に正しいとは断言できないけれども、そこそこ「正しそうな」命題を引き出す数学的な理論を探求し始めるのだ。それが統計学である。そして19世紀以降の国家は、そのような「もっともらしさ」をもとに、人間ひとりひとりに命令するのではなく、人間の群れ(人民)そのものに対してさまざまな政策を施すように変わっていくのである。
生権力はビッグデータを必要とする。その権力は、ぼくの死もあなたの死もすべてをいちサンプルに変えてしまうような、そしてぼくの死もあなたの死もともに予測死者数のいちカウントで表現してしまうような残酷な「場」=統計学を必要とする。郵便的不安は、その場の認識から生まれる。ぼくはいままで、郵便的不安について哲学的に語りすぎてきたのかもしれない。
郵便的不安とは、政治的には生権力が生み出す不安のことである。ぼくはこれからはそのような説明を加えたい。じっさいそれは、30年近くまえの問題意識の出発点に戻っても妥当な言い換えのように思われる。
デビュー作で言及していたかどうか定かではないが、ぼくがそもそも『収容所群島』に深い関心を抱いた理由のひとつは、ソルジェニーツィンがそこで、スターリニズム下における過剰な不当逮捕はもっぱら「目標数字の達成」を目指したことによって引き起こされたと記していたことにあった[★4]。
ソ連は「科学的」な国家だった。だからデータと統計学を信じていた。そしてその科学(史的唯物論)を信じるならば、ある時点のある国家のある地域でどれほどの数の犯罪者が生まれるのかは、小麦の収穫量と同じように正確に予測できなければならなかった。それゆえソ連の秘密警察は、現実をその予測にあわせるべく、粛々と一般市民を逮捕していったのである。ソルジェニーツィンが描いた悲劇は、この意味において統計学の悲劇だった。つまり、生権力の悲劇だったのである。
郵便的不安は、ぼくの死とあなたの死を、あるいはぼくの生とあなたの生を、ともに交換可能ないちサンプルとして扱う、その数の暴力に日常的に曝されることで生まれる不安である。最後につけくわえれば、これまたきわめてアクチュアルな問題でもある。
ぼくはこの4月から6月にかけて、新型コロナウイルスによる混乱のなかで、『ゲンロン11』に掲載予定の6万字ほどの原稿をゆっくりと書き進めていた。主題のひとつは原発事故だった。原稿で直接に生権力を扱ったわけではない。けれどもずっとそのことは考え続けていた。
感染症も原発事故も、加害と被害の関係は確率的にしか記述できない。人々は統計ばかりを語り、そしてみなが確率による不安に振り回されている。ぼくたちはいま確率の哲学を切に必要としている。
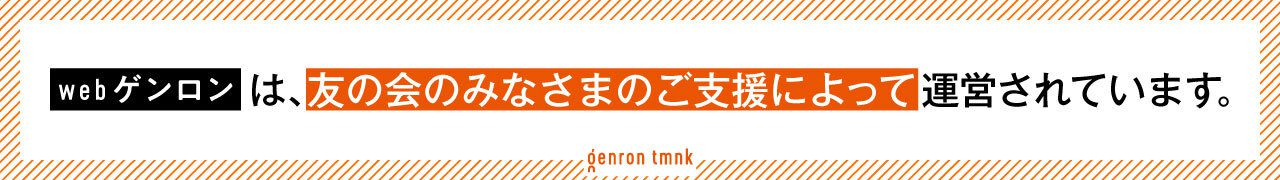

東浩紀
観光客の哲学の余白に
- 観光客の哲学の余白に(26) 訂正可能性と反証可能性|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(25) リベラルと保守を超える|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(24) 顔と虐殺|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(23) 無料という病、あるいはシラスと柄谷行人について|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(22) 郵便的連帯と「接触」|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(21) 郵便的不安と生権力|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(20) コロナ・イデオロギーのなかのゲンロン|東浩紀
- データベース的動物は政治的動物になりうるか
- データベース的動物は政治的動物になりうるか
- 観光客の哲学の余白に(17) 『カラマーゾフの兄弟』は「軽井沢殺人事件」だった――ドストエフスキーとシミュラークル(後)|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(16) ドストエフスキーとシミュラークル(前)|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(15) ウラジオストクのソルジェニーツィン|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(14) 触視的平面の誕生・番外編|東浩紀
- 運営と制作の一致、あるいは等価交換の外部について
- 触視的平面の誕生(3)
- 観光の余白としての哲学
- 観光客の哲学の余白に(10) 触視的平面の誕生(2)|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(9) 触視的平面の誕生|東浩紀
- 崇高とソ連
- 観光客の哲学の余白に(7) まなざしからタッチパネルへ|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(6) 深さの再発明のために|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(5) クレーリーとキットラー|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(4) 表象の秩序と知覚の秩序|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(3)|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(2)|東浩紀
- 観光客の哲学の余白に(1) |東浩紀



