イスラエルの日常、ときどき非日常(8) 第六次ネタニヤフ政権発足──揺れるイスラエルのユダヤ人社会|山森みか

この連載では、現在のイスラエルには宗教や文化を基盤とした様々な集団(宗教派ユダヤ人、世俗派ユダヤ人、アラブ人キリスト教徒、アラブ人イスラム教徒、ベドウィン、ドゥルーズ教徒、父親や祖父母がユダヤ人でも母親がユダヤ人でないため非ユダヤ人と見なされる人々等)があること、そのような人々が相互に一定の距離を保ちつつも市民として共存していることを述べてきた。そしてイスラエルでは18歳から男女共に課される徴兵制(男性約3年、女性約2年)が、これらの異なるグループに属する人々をイスラエル国民として結び付ける役割をある意味で果たしている例も示して来た。今回は、イスラエルにおける最近の政治動向を取り上げたい。
2022年11月に行われた総選挙で、約1年半に亘って下野していたビンヤミン・ネタニヤフ(リクード党首)が首相の座に返り咲くことになった。2か月もかかった諸政党との連立交渉の末、同年12月29日に第六次ネタニヤフ政権が発足した。このニュースは、海外ではイスラエル史上最も強硬な右派政権発足として、パレスチナ問題悪化への懸念と絡めて報じられることが多かった。だが国内からは、これを機にイスラエル社会そのものが大きな転機を迎えたように見える。一定の距離と緊張を保ちつつ共存してきた諸集団の間に以前からあった亀裂、とりわけユダヤ人内部の考え方の相違が、新政権誕生を機に明確に可視化されたからである。しかも、ただそれが可視化されただけでなく、異なる集団に対する嫌悪が増大しつつある。新政権に反対する声は広がる一方で、毎週安息日明けの土曜日夜に行われる市民たちの大規模デモに加え、イスラエル経済を牽引するハイテク業界のスト、さらにはイスラエル国防軍の戦闘機パイロット部隊予備役の訓練拒否宣言にまで反対運動が広がり、物議を醸している[★1]。
民主的に行われた選挙結果を受けて発足した新政権のはずなのに、なぜこれほど揉めているのか。簡単に言えば、それは収賄罪等で起訴され公判中のネタニヤフが、有罪判決から服役という道筋を避けるために、なりふりかまわず政権を奪い返す行動に出たことに起因する。
イスラエルの国会(クネセト)は、議席数が120の一院制である。いわゆる右派と左派の二大政党が勢力を二分し、その間でユダヤ教超正統派の小政党がキャスティングボートを握るという体制が長く続いてきた。いずれの大政党も自分たちだけでは多数派になれないので、やむを得ず超正統派の宗教色が強い小政党の言い分を聞いて、ようやく政権を維持してきたとという経緯がある。だが時代が移ると、主張が細分化されて中小の政党が乱立するようになり、どの政党がどこと連立を組めば政権が成立するかが、選挙における主たる関心の焦点となった。中小政党の乱立は、イスラエル国民の考え方の多様性を象徴するという側面もあるが、政治的な不安定さの原因でもある。ネタニヤフ率いるリクードも、第一党とはいえ今回の選挙で32議席しか獲得できていない。
なぜ今回ネタニヤフは、数ある政党の中から危険な主張をする極右政党と連立を組まなければならなかったのか。ネタニヤフを党首とするリクード党がかつて連立を組んできた、比較的穏健な右派政治家たちの中には、ネタニヤフ個人を支持しないと表明した人々がかなりいる。だからこそ反ネタニヤフを旗印にしたナフタリ・ベネット/ヤイル・ラピード政権が2021年に誕生し、紆余曲折がありながらも1年半続いたのである。ベネットは宗教右派政党ヤミナ、ラピードは中道のイェシュ・アティッド(有未来)党の党首であり、彼らの政権には左派政党とアラブ政党も参加していた。政権復帰の機会を狙っていたネタニヤフは、この「極右から極左まで」と評された政権の脆い基盤の切り崩しに成功し、解散に追い込んだ。
その背景には、宗教右派政党ヤミナ党首のベネットが、反ネタニヤフを旗印として左派やアラブ政党と組み、連立政権を立てたことを「裏切り」と感じていた同党議員たちの存在があった。ネタニヤフはこうした議員たちの取り込み工作には成功した。しかし、反ネタニヤフを掲げる比較的穏健な右派と組む道はもはや塞がれていた。そのため彼は、従来連立を組んできたユダヤ教超正統派の政党(ベネット/ラピード政権時はネタニヤフと共に野党に回っていた)だけでなく、「極右」と称される宗教シオニズム諸政党とも連立を組まざるを得なかったのだ。これが「現政権の中で最も中道的立場なのはネタニヤフ」「ネタニヤフは保身のため極右政党の人質となった」等と評される理由である。
今行われている大規模な反政権デモは、新政権が推進する司法制度改革にノーを突き付けることを目的として始まった。この司法改革案は、法務相に任命されたヤリブ・レビンによって発表されたのだが、その内容を要約すると、国会(クネセト)で過半数の賛同を得られれば最高裁の決定を覆せるし、裁判官の選任に政府の意向を反映させられるということになる。民主主義社会における議会と司法の関係のあり方については諸議論があって然るべきだろう。この改革案には、あまりにも「左」に寄りすぎた最高裁の判断に縛られて自由な政権運営ができないという批判が常々為されてきたという背景もある。
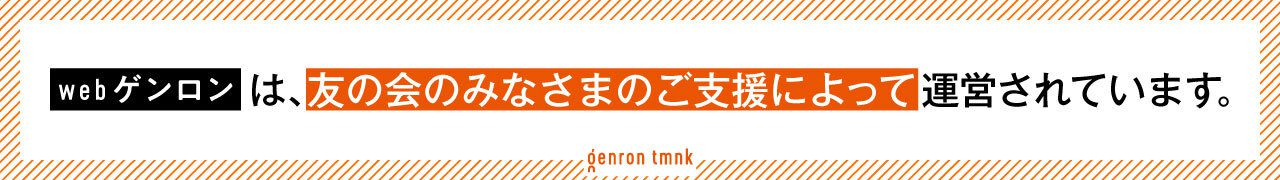

山森みか
イスラエルの日常、ときどき非日常
- 「二級市民」という立場 イスラエルの日常、ときどき非日常(9)|山森みか
- イスラエルの日常、ときどき非日常(8) 第六次ネタニヤフ政権発足──揺れるイスラエルのユダヤ人社会|山森みか
- 兵役とジェンダー(2)
- ホロコーストへの言及をめぐって(初出:2022年10月25日刊行『ゲンロン13』)
- イスラエルの日常、ときどき非日常(5) 兵役とジェンダー(1)|山森みか
- イスラエルの日常、ときどき非日常(4) 共通体験としての兵役(3)|山森みか
- イスラエルの日常、ときどき非日常(3) 共通体験としての兵役(2)|山森みか
- イスラエルの日常、ときどき非日常(2) 共通体験としての兵役(1)|山森みか
- 現代イスラエル人とは誰か(初出:2021年9月15日刊行『ゲンロン12』)




